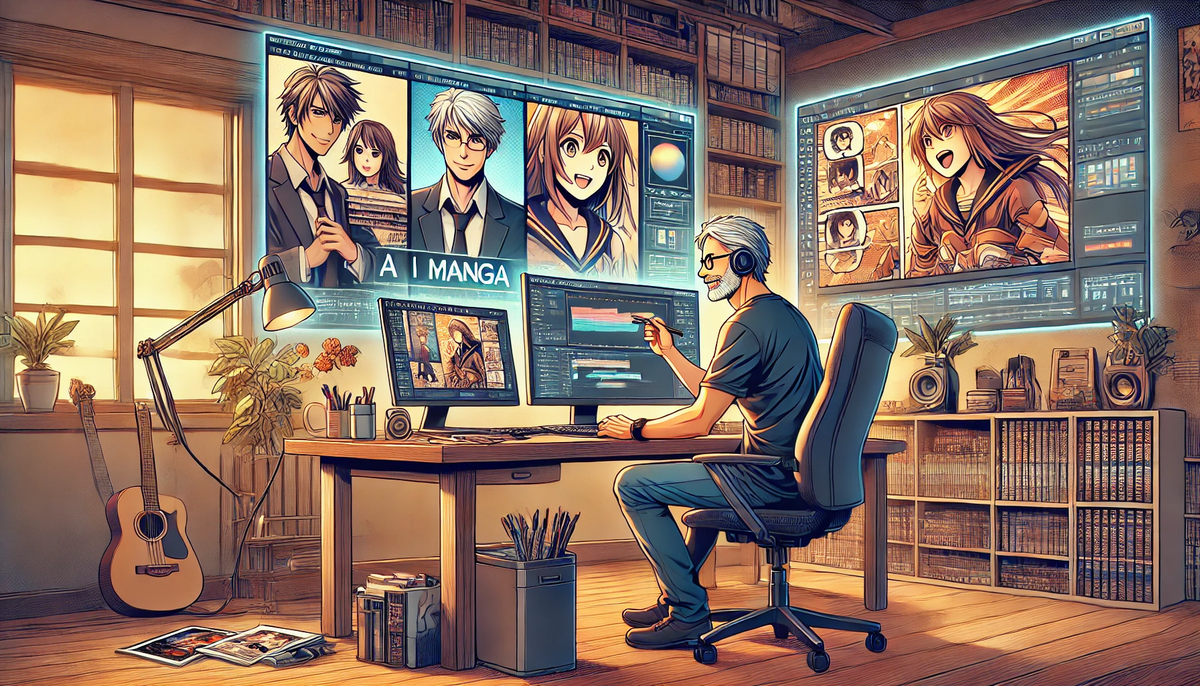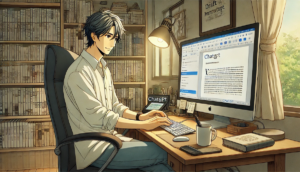AI漫画は、絵が描けない人でも創作できる、まったく新しい表現手段です。
ツールをうまく活用すれば、あなたの頭の中にあるストーリーを「漫画」という形にして誰かに届けることができます。
とはいえ、初めて取り組む方にとっては、「どうやって作るの?」「何を使えばいいの?」と疑問が尽きませんよね。
筆者自身もまったくの初心者からAI漫画制作をスタートし、試行錯誤を重ねてきました。
この記事では、ストーリー作成からキャラ生成、構成編集、セリフ入れ、そして副業活用まで、AI漫画の作り方をステップごとにわかりやすく解説します。
どこから手を付けていいかわからないという方でも、読み終わるころには「自分にもできそう」と感じていただけるはずです。
- AI漫画とは何か、どんな魅力があるのかが分かる
- ストーリー作成から完成までの4ステップを具体的に解説
- Anifusion・Canva・Frameplannerの活用術を実体験ベースで紹介
- 副業や発信手段としての活用アイデアも紹介
- 初心者でもすぐ始められるノウハウが満載
 Tane
Tane私はAI漫画帝国というスクールでAI漫画を学び、ゼロから二か月間で『もしも社長がPTA会長になったら?』というAI漫画を出版しました。この記事ではAI漫画制作の大まかな流れを紹介します。
AI漫画とは?仕組みと魅力をやさしく解説
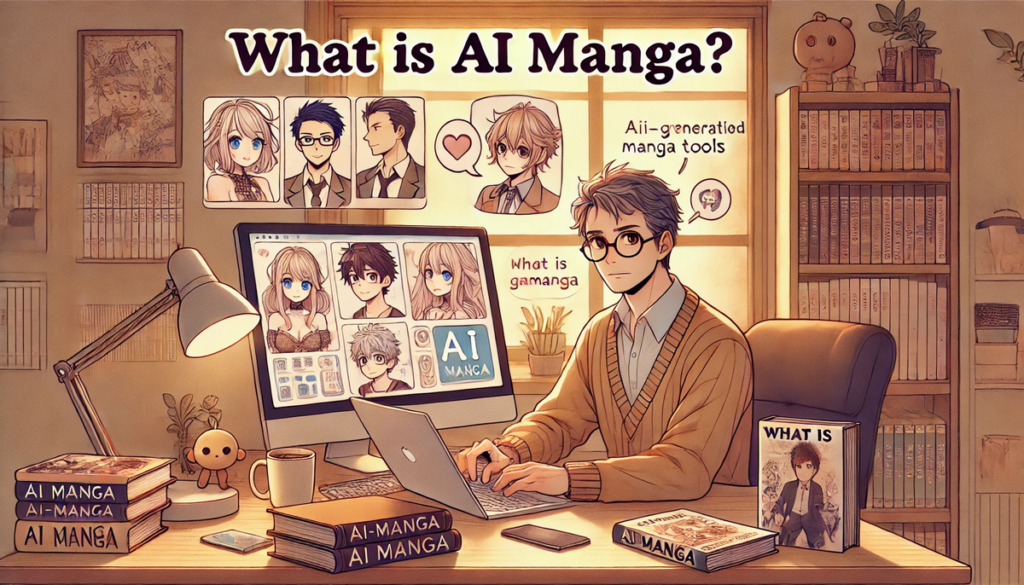
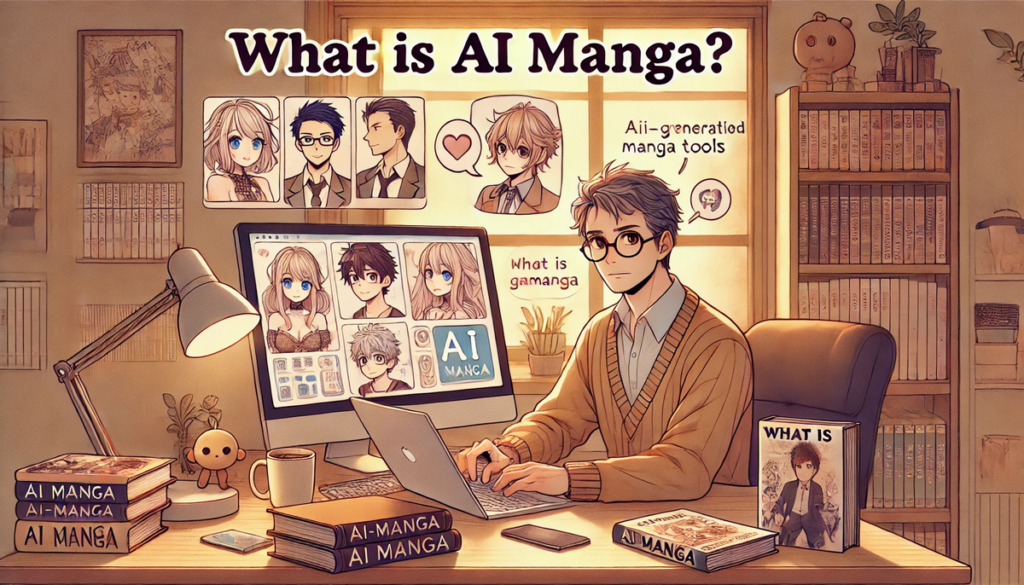
AI漫画の定義と最近のトレンド
AI漫画とは、AI技術を活用してキャラクター画像やストーリー、構成などを生成・編集して制作された漫画のことです。
従来のようにすべてを手描きや手作業で行うのではなく、画像生成AI(例:Anifusion、Midjourneyなど)や文章生成AI(ChatGPTなど)を組み合わせることで、より短時間で漫画を作ることが可能になっています。
近年では、SNSを中心にAI漫画を発信するクリエイターが増え、AI漫画専門の書籍やコミュニティも登場するなど、非常に活気のある分野へと成長しています。
AI漫画が注目される理由(副業・表現手段として)
AI漫画が注目される背景には、いくつかの大きな理由があります。
まず一つは副業の手段としての可能性です。誰でも手軽に始められ、SNSや投稿サイトを通じて発信できるため、収益化までのスピード感もあります。
もう一つは、自己表現の場としての自由度の高さです。
筆者は50代の会社員ですが、AI漫画を副業の一つとして考え、25年の1月から勉強を始め一冊目を出版しました。
実際に作ってみて、ストーリーをどう構成すればいいのか、キャラの見た目をどう固定するかなど多くの壁にぶつかりましたが、AIのサポートがあるからこそ、乗り越える楽しさがありました。
特に印象に残っているのは、コマ割りに悩んだときに「AI漫画帝国」の先輩たちの書籍を参考にして、少しずつ形になっていった経験です。
「プロでなくても、自分の物語が形になる」ーーその喜びこそが、AI漫画がこれほどまでに支持される大きな理由なのかもしれません。
AI漫画作成に必要な4つのステップ


Step1. ストーリーを考える(構成とセリフの土台)
AI漫画制作の出発点は、ストーリーの素案作りです。
筆者はChatGPTを活用して、ビジネススキルの漫画化を目指し、セリフ作成に取り組みました。
しかし当初は、プロンプトがうまく組めずに大苦戦しました。
セリフの量が足りなかったり、章ごとに無理に起承転結をつけようとして不自然な展開になることもありました。
試行錯誤の末、まずテキストベースでノウハウ本のような内容をChatGPTでまとめ、それを土台にして「登場人物4人のセリフ」に変換する形にしたところ、ようやくうまく生成することができました。



この時に作ったノウハウ本を生成するGPTsの改良版はこちらの記事で無料公開しています。ノウハウ本からセリフに落とし込むGPTsは現在改良中なので完成したら公開予定です。
Step2. キャラクター・画像の生成(Anifusionなど)
キャラクターの生成にはAnifusionを使用しました。
私が学んだAI漫画帝国はAnifusion縛りがありましたが、MidjourneyやStable diffusionを使える方はそちらでも大丈夫です。
背景はCanvaの素材やAnifusionで別に作るので、下の画像のようなシンプルな背景のキャラ画像をセリフやシナリオに合わせて生成していきます。


その際、キャラクターの特徴をプロンプトで指示して、ぱっと見同じキャラクターに見える画像を生成できるプロンプトを探っていきます。
私の場合、女性キャラは比較的簡単にキャラ固定できたのですが、男性キャラの生成では毎回明らかに異なるキャラが出力され苦戦しました。
しかし、途中でAnifusionにアップデートが入り、「キャラを学習させる機能」が搭載されたことで状況は改善。
同じ特徴を持つキャラクターを複数のポーズや表情で生成できるようになり、ようやく漫画としての連続性が保てるようになりました。
Step3. 背景や構成の加工(Canva)
次に必要なのが、Canvaを使ってAnifusionで生成したキャラ画像の修正と背景除去、Canvaの素材を使って背景の準備です。
Canvaは、画像の修正や背景除去などAI漫画に必要な機能が盛り沢山なので、その機能を使ってAnifusionで生成した際に途切れていた画像を補完したり、背景を除去していきます。
また、Canvaには背景に使える素材が沢山あるので、それを使って漫画の背景画像を準備していきます。
背景に使えそうな画像がない場合にはAnifusion等で人がいない背景画像を生成しましょう。
Step4. コマ割りとセリフ入れ(Frameplanner)
最後に、漫画としての完成形に仕上げる工程です。
Frameplannerを使えば、画像を並べながら自由にコマ割りができ、セリフの入力もスムーズです。
筆者は当初、コマ割りに変化をつける方法が分からず、単調な構成になりがちでした。
そこで、AI漫画帝国の先輩クリエイターによる解説本を読み、視線の流れや構図のバランスについて学習。
実際に試してみることで、読みやすく自然なレイアウトを意識できるようになりました。
AIによる自動生成を活用しつつ、創作者自身の工夫も必要なこのパートは、完成までの達成感が大きく、非常に充実感のある工程です。
ストーリーと構成を考える|テーマとセリフの作り方
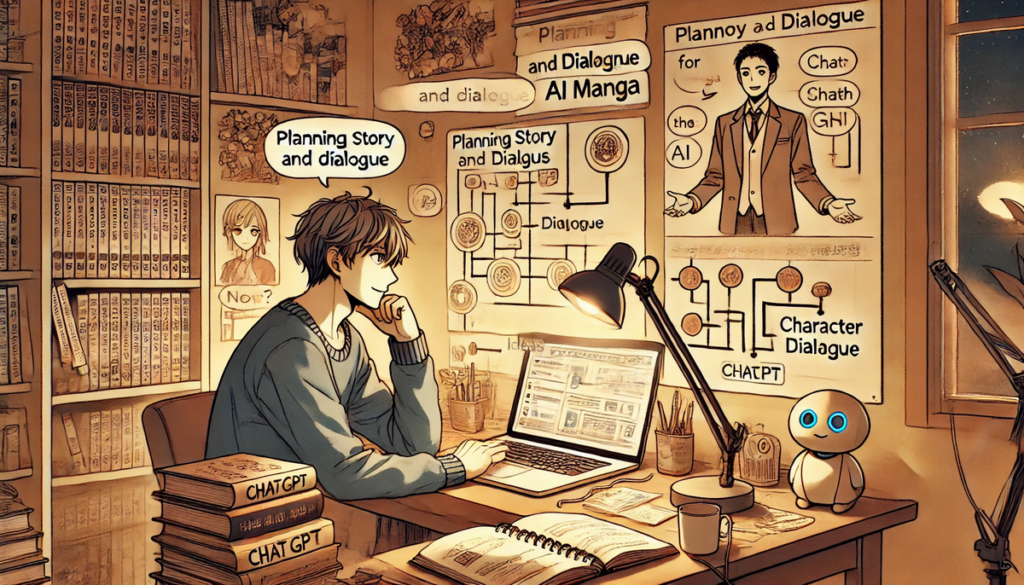
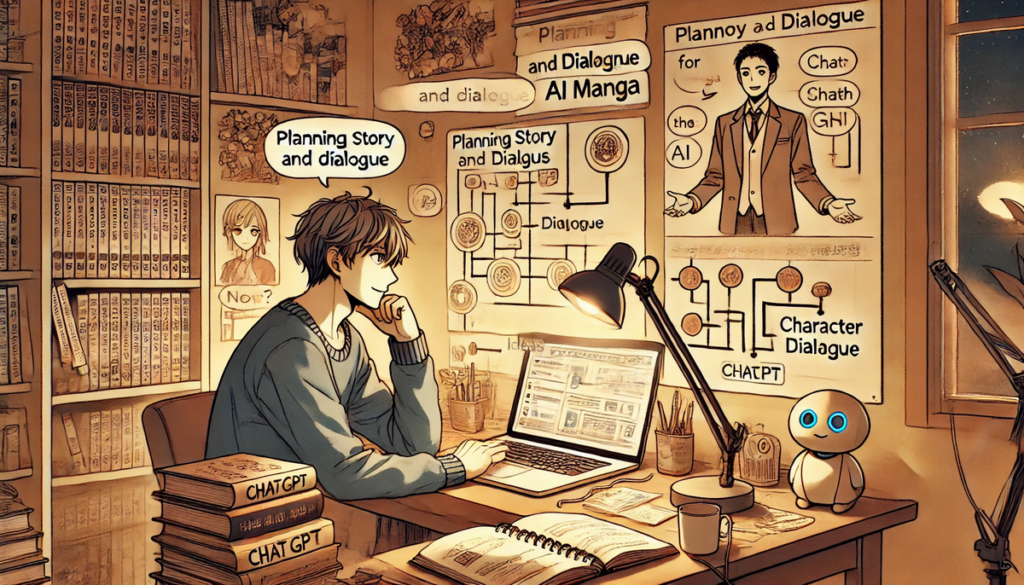
ストーリー構成の基本(起承転結や三幕構成)
AI漫画においても、ストーリーの骨組みは非常に重要です。
「起承転結」や「三幕構成(序破急)」といった構成法は、物語にメリハリを生み、読者を惹きつけるための土台になります。
ただし、AIに任せると機械的な構成になってしまいがちです。
そのため、まずは自分自身で大まかなテーマや方向性を決めておくことが重要です。「誰が」「何に悩み」「どう乗り越えるのか」を整理するだけで、ストーリーに深みが出てきます。
セリフ作りと感情表現の工夫
ストーリーが固まったら、次はセリフ作りです。
筆者の場合、最初はChatGPTに大まかなストーリを渡してセリフを生成させていましたが、「セリフの量が少ない」「内容に重複・矛盾がある」といった課題がありました。
最初の本がビジネスノウハウ系の物語だったこともあり方針を変え、まずはテキストベースで“ビジネス系ノウハウ本”の内容をまとめ、それを登場人物4人のセリフへと変換するアプローチに切り替えました。
この方法が非常にうまく機能し、自然な流れでセリフを生成することができました。
この一連のプロンプト作成ノウハウは、いずれGPTsとして公開したいと思っています。
ChatGPTでストーリー作成する際の注意点
ストーリー作りにおいて、ChatGPTは非常に強力な相棒になります。
単に「漫画のネタを出して」と頼むのではなく、「○○というテーマで悩む会社員が、△△をきっかけに変化していく話」など、背景・登場人物・テーマを具体的に伝えることで、より精度の高いストーリーを引き出せます。
また、「場面ごとの会話例」「各キャラの口調の特徴付け」なども、プロンプトで調整が可能です。
筆者もこうした使い方を通じて、「AIは道具、自分は演出家」というスタンスを意識するようになりました。
ストーリーとセリフの相互作用が整ってくると、作品全体に芯が通り、読者にとっても印象的な漫画に仕上がります。
キャラクターを作ろう|Anifusionの使い方


プロンプトの基本とコツ
AI漫画においてキャラクターは、読者の印象を左右する最重要要素です。
Anifusionは、プロンプト入力によって表情やポーズ、服装などを自由にカスタマイズできる画像生成ツールです。
まずは「性別・年齢・服装・視点」などを具体的に記述し、何度か生成して外観がブレ難い組み合わせを見つけましょう。
その際、プロンプトはGAZAIというサイトで作成するとプロンプトを英語で取得できるので便利です。
生成AIで画像を生成する際、皆さんご存じのように指や手の本数が多かったり少なかったりする問題が生じます。
それを避けるためにネガティブプロンプトを入れる必要があるのですが、私が使ったネガティブプロンプトはAI漫画帝国で教わったものなので著作権の関係上開示できません。
キャラの表情やポーズのバリエーション作成
筆者が特に苦戦したのは、男性キャラクターの一貫性です。
Anifusionで生成される男性キャラは、微妙どころか「明らかに別人」と言えるほどバリエーションが激しく、同じ人物として扱うのが難しい状態でした。
途中でAnifusionにアップデートが入り、「キャラクターを学習させる機能」が追加されたことで状況が改善。
特定の人物設定をもとに、異なるポーズや表情のバリエーションを安定して生成できるようになりました。
この機能を活用することで、表情を変えたり体の向きを調整したりしながら、物語の展開に応じたキャラの感情表現がしやすくなります。
また、作品全体に統一感が出るため、読者にとっても違和感なくストーリーに没入できるようになります。
一貫性のあるキャラ作りは、AI漫画制作において意外と大きなハードルですが、ツールの進化と工夫で確実に乗り越えることが可能です。



生成AIで画像を生成する場合全く同じキャラを出すのは難しく、複数生成した画像から選ぶなど、ある程度の妥協は必要です。
5. 背景や素材を整える|Canvaの活用術
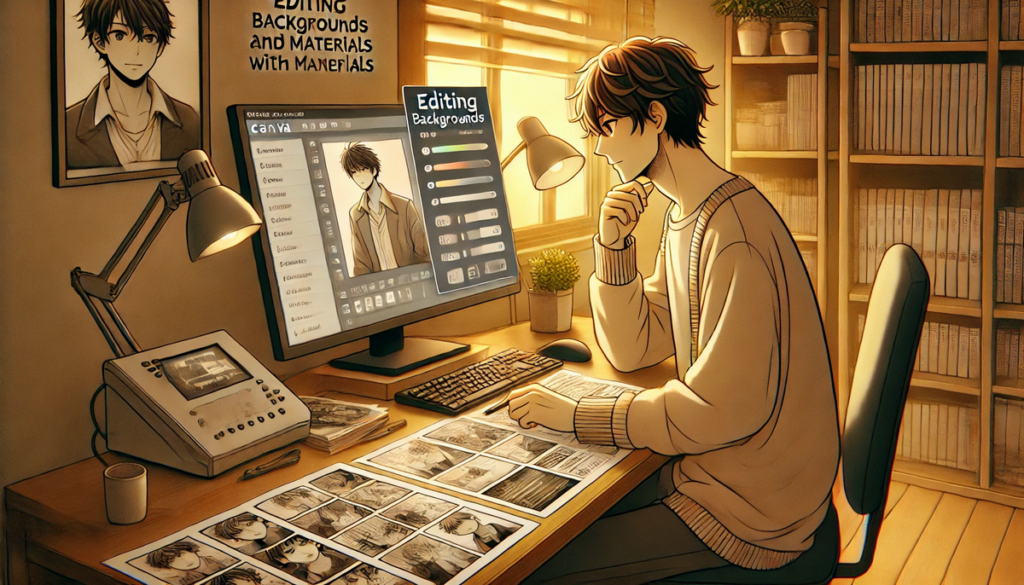
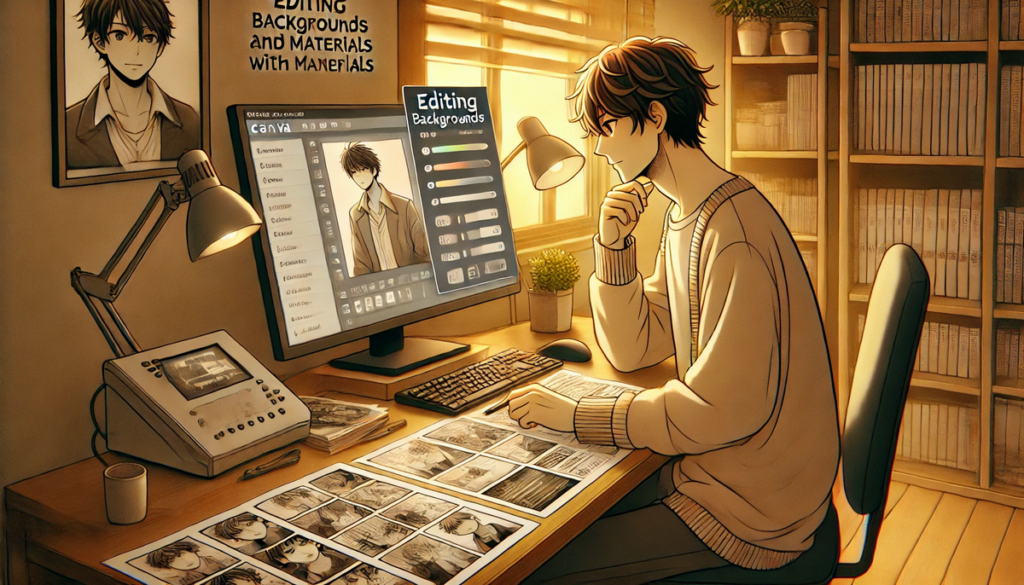
背景除去、トリミング、画像補完の手順
AIで生成されたキャラクター画像は、必ずしも“完成された状態”ではありません。
Anifusionで生成した画像は構図によってはキャラの髪や手足の一部が枠からはみ出して描かれず、画像の端が不自然に切れてしまうことがありました。
そうした場合に役立つのが、Canvaの「マジック生成」機能です。
これは、画像の欠けた部分をAIで補完し、自然な見た目に整えてくれる非常に便利な機能です。
筆者も、髪の毛の端や肩のラインが不自然に途切れていた画像を、マジック生成で補うことで、違和感のない仕上がりに整えることができました。
どうしても自然に補完できないときには、吹き出しをうまく重ねて欠けた部分をカバーしたり、小回りで構図ごと見せないように調整することで対応しています。
こうした工夫を怠ると、読者に「この作品は雑だな」という印象を与えかねません。
一見細かい部分ですが、こうした丁寧さこそが作品全体のクオリティを大きく左右します。
素材の統一感を出すポイント
キャラや背景、構図がバラバラだと、読者はストーリーに集中しづらくなります。
Canvaのフィルターやエフェクト機能を使えば、画像同士のトーンや色調を揃えることができ、作品としての統一感が生まれます。
特に背景や小物などは、他ツールで作った素材と混在しやすいため、同じ明るさ・彩度に調整するだけでも印象がぐっと変わります。
AIによる画像生成に任せるだけではなく、最後に“人の目”で整える仕上げ工程が、作品を一段上のレベルに引き上げてくれます。
6. 漫画として形にする|Frameplannerでの制作手順


コマ割りの基本ルールと配置の工夫
漫画を「読み物」として完成させるためには、キャラ画像や背景を並べるだけでなく、物語の流れに沿ったコマ割りと配置が欠かせません。
Frameplannerは、コマのサイズ・配置を自由にカスタマイズでき、セリフや画像を組み合わせて一つのページとして仕上げることができます。
筆者の制作工程では、まずセリフを先にコマに配置し、それに合わせてキャラクターや背景を後からはめ込んでいくスタイルをとっています。
この順番にすることで、セリフの分量やテンポに合わせたレイアウトが可能になり、後から調整しやすくなるのがメリットです。
コマ割りの工夫と学びの実践
コマ割りのデザインは、読みやすさや感情の盛り上がりに大きく影響します。
筆者がAI漫画制作を始めた当時、AI漫画帝国ではまだコマ割りを専門的に扱った情報が少なく、自分なりに手当たり次第先輩たちの作品を読み漁りました。
その中で、上手な方のコマ構成を観察し、自分の実力や作風に合ったものを真似して実践することを心がけました。
セリフ配置と画像構成のポイント
Frameplannerでは、セリフ用の吹き出しも簡単に追加できます。
筆者は、セリフが決まったらまずそれを元にページ全体の構成を考え、その後キャラクターや背景の画像をはめ込み、場面を仕上げていくという流れで作業しています。
この順序にすると、画像や構図にとらわれすぎず、物語のリズムや読みやすさを優先できるため、結果として自然な流れのある作品になります。
7. 作品を公開しよう|発信・保存・副業のヒント
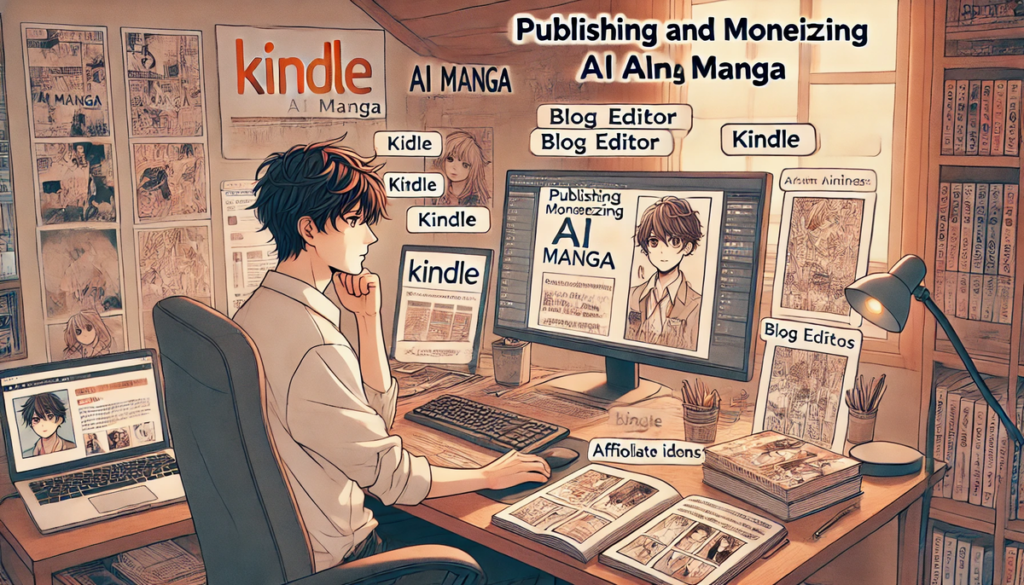
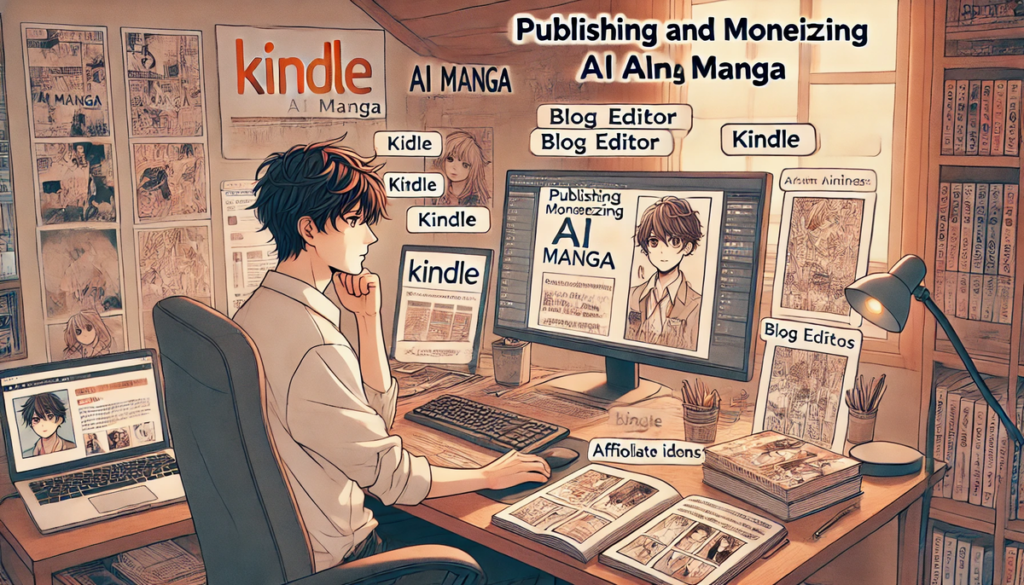
SNS・ブログ・投稿サイトでの公開方法
AI漫画が完成したら、いよいよ誰かに届けるステップです。
SNS(X、Instagram)、ブログ、noteなど、無料で使えるプラットフォームが充実しており、発信のハードルは非常に低くなっています。
最近では、1ページ完結やショート形式の漫画をSNSで投稿し、制作中の長編漫画やシリーズ作品のPRとして活用している作家も増えています。
読者の目に触れる機会が増えることで、反応やフォロワーとの交流から新たなヒントが得られることもあるでしょう。
特にX(旧Twitter)は拡散力が高く、初見の読者にも届きやすいため、AI漫画との相性も良好です。
商用利用と著作権の注意点
AI漫画を副業やビジネスに展開していく場合、ツールの利用規約や著作権についての確認は欠かせません。
Anifusionは商用利用が許可されているAI画像生成ツールで、筆者もその規約を確認したうえで活用しています。
ただし注意すべき点として、生成されたキャラクターが既存の人気作家の絵柄に似すぎてしまう場合があるということがあります。
このような場合は、作品の信頼性や法的リスクを避けるためにも、差し替えるなどの対応が望ましいでしょう。
商用活動を見据えるなら、誰が見てもオリジナリティを感じられるキャラクター作りを意識することが大切です。
副業としての展開アイデア
AI漫画を副業に活用する方法は多岐にわたります。
以下のような展開は、実際に成果を上げているクリエイターも増えており、筆者自身も今後取り組んでいく予定です。
- 自作の漫画をKindle出版して販売
- ストーリー漫画を使ったアフィリエイト(商品紹介型)
- スキルマーケット等での漫画制作代行の外注受注
- 自分のサービス紹介ページや教材で使うLP用コンテンツ制作
漫画というフォーマットは、専門的な内容やサービス紹介をわかりやすく伝える手段として非常に優れています。
AIの活用によって、従来よりも圧倒的に短時間・低コストで制作できるため、「絵が描けない人」でも挑戦可能な副業ツールとして大きな可能性を秘めています。
これからの時代、伝える力と構成力をAIと組み合わせることで、誰でも漫画を通じたビジネス展開ができるようになるでしょう。
8. まとめ|AI漫画づくりは誰でも始められる!
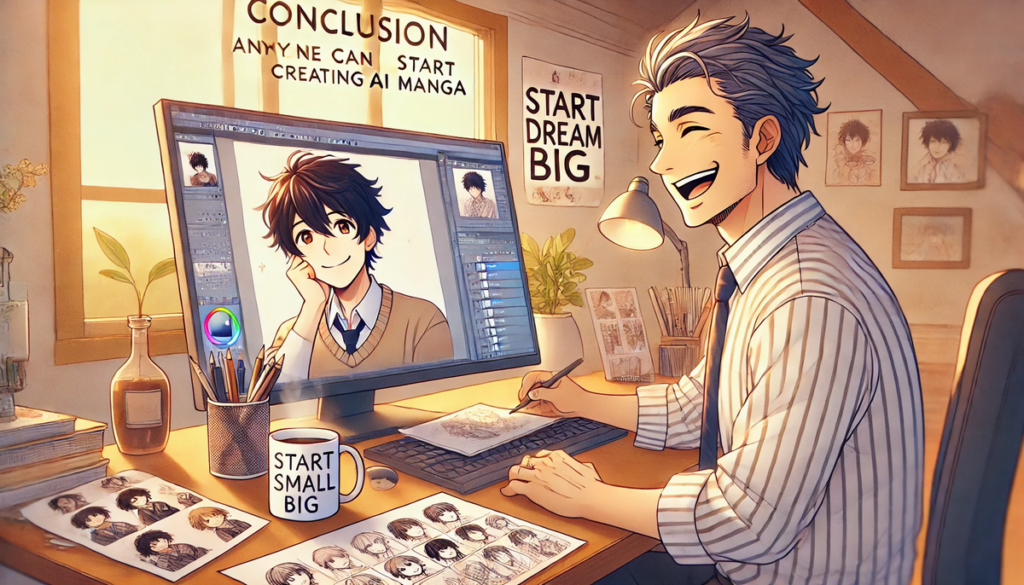
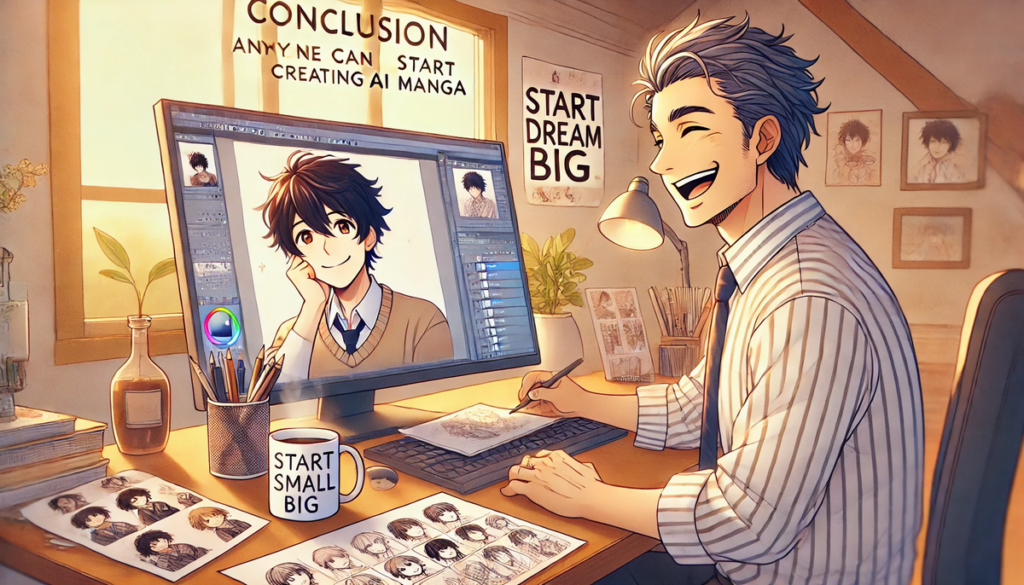
AI漫画は、もはや一部の限られた技術者やアーティストだけのものではありません。
画像生成AI、文章生成AI、そして優れた編集ツールの登場により、誰でも自分だけの漫画を形にできる時代が到来しました。
筆者自身、ストーリー作成やキャラの一貫性、コマ割りの構成など、数々の壁にぶつかりました。
それでも、AIの力と自分の発想を掛け合わせることで、「創作は自分にもできる」と確信を持つことができました。
AI漫画制作のプロセスは以下のような4ステップに整理できます:
- ストーリーを考える(テーマ・セリフ構成)
- キャラクターを生成する(Anifusion)
- 背景・素材を整える(Canva)
- コマ割りとセリフを入れて仕上げる(Frameplanner)
それぞれの工程に工夫の余地があり、経験を積むごとに表現の幅が広がっていきます。
さらに、完成した作品を発信することでフィードバックを得たり、副業につなげたりする道も拓けてきました。
Kindle出版、アフィリエイト、外注受注、自分の商品紹介など、漫画というフォーマットは“伝える力”として非常に優れたツールです。
はじめの一歩は、完璧を目指さなくて大丈夫です。
まずは、「自分のアイデアを形にしてみたい」という気持ちからスタートしましょう。
AI漫画は、今この瞬間も進化を続けており、これから創作を始める方にとっても、大きな可能性が開かれています。
あなたも、今日から物語を描く“作者”になってみませんか?
あなたの創作が、誰かの心に届く一歩になりますように。
↓下記はPRです。生成AIを基礎から学びたい方にお勧めのセミナーです↓